市井の音楽教室での、練習楽曲の使用に著作権料が発生するか否か。徴収側(JASRAC)と、それを否定する教室側(その先頭に立つのはヤマハ音楽振興会)との争いも、いよいよ本番を迎えた。6月7日配信の時事通信のネットニュースによると
日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、東京都内で記者会見を開き、ピアノなどの音楽教室での演奏について、来年1月から著作権料の徴収を始めると正式に発表した。 同日、文化庁に使用料規定を届け出た。
ということだ。これに先んずる形でヤマハ側はJASRACに対し、支払義務不存在の確認訴訟を予告している。どちらが勝つにしても、決着は法廷を経て、ということになる。
実際のところ、教室では著作物である楽曲の楽譜を使用し、金銭の授受が発生している。教室が営利事業として運営されているという面からすれば、法廷においてはJASRACに分があるだろう。そうわたしは思う。
ではJASRACがあきらかに正当なのかといえば、それは単純にそうではない。音楽著作権、音楽で発生する権利、またその扱いの慣習というものは、一筋縄で括れるというものではないからだ。
まず音楽著作権の代表的なものである作曲家による著作権というものがある。曲から発生する著作権である。しかしそれだけでは音楽にはならない。実際に音にする演奏家が必要である。しかし演奏家の権利は、著作権より一段低いものとして見做されており
音楽著作権の重層性
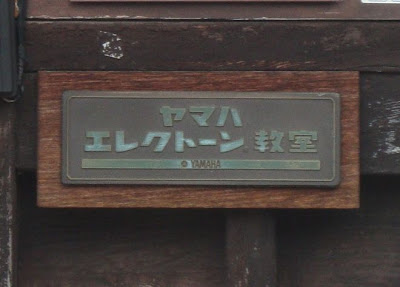 経済ニュース
経済ニュース


コメント