中小企業の共創プロジェクトに見る、境界線をなくす意義
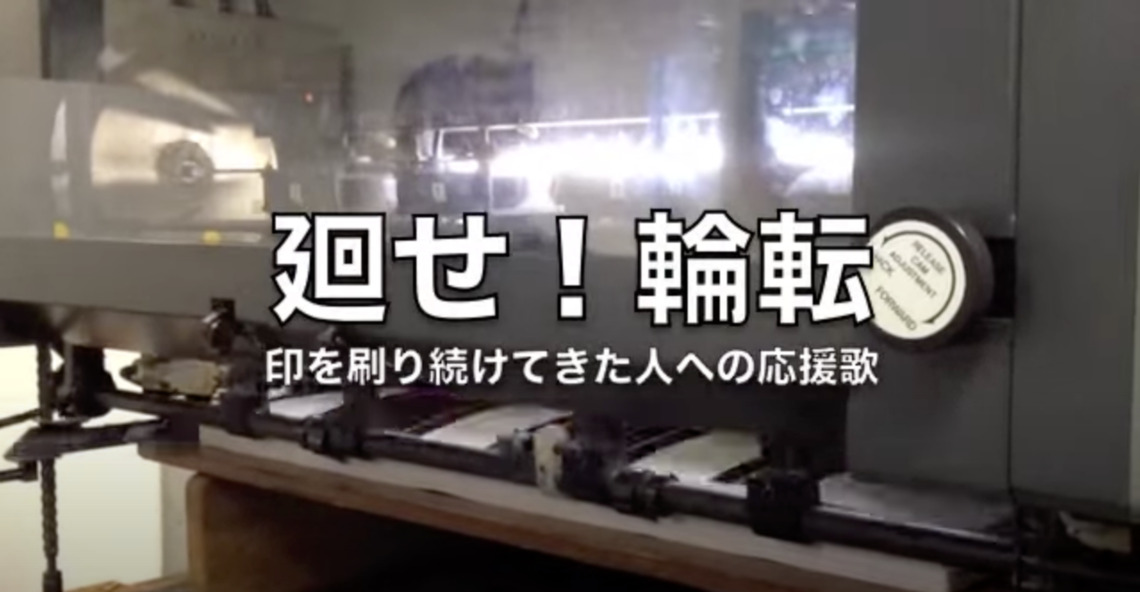 マーケティング最新
マーケティング最新中小企業のコンテンツメーカーとしての魅力や可能性に迫る本連載。
今回話を伺ったのは、中小企業の社員主導イベント「工場ライブセミナー」を実施する「情熱の学校」エサキヨシノリ氏と、地域・企業を巻き込んだ対話型映画「未来シャッター」ムーブメントをリードするワップフィルム代表の高橋和勧監督。
両プロジェクトに参加した経験を、自身の企画開発に生かす電通の森本紘平が、心を揺さぶるコンテンツメイキングのポイントを聞きました。
中小企業ならではの課題解決手法「工場ライブセミナー」
森本:僕はお二人のプロジェクトからさまざまなヒントを得ました。また、その経験を生かして立ち上げた「社歌コンテスト」にも、情熱の学校とワップフィルムには協力名義でご参画いただいています。まずはお二人のプロジェクトを改めて教えていただけますか?
エサキ:僕がやってきたのは「工場ライブセミナー」です。一言でいえば、「工場で行う、歌を通じた中小企業のためのビジネスセミナー」ですね。皆さんにお見せする景色としては、製造業の工場で社歌を含めた歌を歌っているということなんですけど、実は本番の8カ月ほど前から該当企業の若手社員を中心にプロジェクトチームを作り、月1回のミーティングをしていきます。その過程で自分たちの会社を知ることができるし、歌にアウトプットする上で、大切なことを言葉にできる点も大きい



コメント